
仏教や悟りの世界ってふかーい印象があります。その触りだけでもと、お坊さんYouTuberである武田正文さんにお伺いしました。質問をするたびに「そういうものではないんです」という回答をいただき、私は普段どれだけ固定観念にとらわれているのだろうかと感じましたね。少しだけ、仏教の入り口(?)が見えたかもしれません。
 栃尾
栃尾クリエイティブの。
 武田
武田反対語。
 栃尾
栃尾こんにちは、ストーリーエディターの栃尾江美です。
 武田
武田こんにちは、お坊さんYouTuberの武田正文です。
 栃尾
栃尾このポッドキャストは私、栃尾江美が好きな人やお話したい人をお呼びして、クリエイティブに関することや哲学的なことを好き勝手に話す番組です。はい、えっと、では、5回目ですね、武田さん、よろしくお願いします。
 武田
武田はい、お願いします。
 栃尾
栃尾ようやく仏教のことをね、お伺いしようかなと思って(笑)。
 武田
武田はい、ぜひ、ぜひ。
 栃尾
栃尾仏教ってですね、私なんか色々本を読みたいなと思いつつ、結構哲学とかも好きだったりするので、その本を読みたいなと思いつつ、毎回挫折するんですけど、途中で。
 武田
武田はい、はい。
 栃尾
栃尾でも、結構読み切れたなと思うのが、アルボムッレ・スマナサーラさんの。
 武田
武田はい、はい。
 栃尾
栃尾本を何冊か読み切れたんですよね。
 武田
武田あぁ、いいですね、いいですね。
 栃尾
栃尾結構言ってることが、なんか本当っぽいなっていうか(笑)。
 武田
武田ホントですよ、すごい……。
 栃尾
栃尾上辺じゃないなみたいな。
 武田
武田えぇ、えぇ。
 栃尾
栃尾感じがして面白かったですけど。お会いしたことあるってさっき仰ってましたね?
 武田
武田はい、そうなんです。私もですね、スマナサーラ長老の瞑想会に2回かな? 行ったことがあって。
 栃尾
栃尾瞑想する会なんですか?
 武田
武田そう、そう。あの、私はですね、浄土真宗っていうのは実は瞑想とか座禅ってやらないんですよ。
 栃尾
栃尾あ、はい。へぇ。
 武田
武田やらなくて、だから全然知らないんですけど、たまたま知り合いのお坊さんがいて、「スマナサーラ長老が来るから、ちょっと体験としてやってみないか」っていう風に言われて、「それはちょっと行ってみよう」っていうことでですね、行って受けたんですけど、面白くって、やっぱり仏教の基本になるんですよね。
 栃尾
栃尾へぇ。
 武田
武田で、スマナサーラ長老がやっておられるのが、テーラワーダっていって、上座仏教ですね。タイとか、スリランカとか、その日本に来た仏教じゃなくて、インドに昔から残ってる仏教で、昔のまま残している仏教なんですよ。
 栃尾
栃尾ふーん。
 武田
武田その根本的なプラクティスを教えてくれたんですけど、こう歩く瞑想とかね。ゆっくり歩くんですよ。
 栃尾
栃尾はい。
 武田
武田めちゃくちゃゆっくり歩くんですよ。
 栃尾
栃尾はい、止まってるかのように(笑)。
 武田
武田止まってるかのような速度で歩いて、関節の動きを感じるとか。
 栃尾
栃尾あぁ。
 武田
武田で、手を上げるのも「ゆっくり上げなさい」とかって言われるんですよ。もうあれがね、すごい新鮮な感覚で、「あぁ、こういう世界があるんだな」って思って、体験した記憶があります。
 栃尾
栃尾ふーん。面白い。
 武田
武田うん、長老の本だと、僕好きなのは、『怒らないこと』っていう本があって。
 栃尾
栃尾あ、読みました。
 武田
武田あれがすごい良い本だなって、もうバイブルですよ。怒ったときいつもあの本を思い出します。
 栃尾
栃尾(笑)なんだっけ、なんか「突然後ろから、よく訳の分からない人が来て、殴られて、殺されたとしても怒るな」っていう話ですよね(笑)。
 武田
武田そう、そう、そう(笑)。すごいなって思って(笑)。
 栃尾
栃尾(笑)もうそれ、忘れられない(笑)、忘れられないっていうか(笑)。
 武田
武田格好いいんですよね、表現がね、色々。
 栃尾
栃尾そうですね。
 武田
武田結構スマナサーラ長老、ズバズバ言う人だから。
 栃尾
栃尾あぁ。
 武田
武田なんかすごいんですよ、言い方とか。生で聞くとよりすごいですよ。
 栃尾
栃尾へぇ。
 武田
武田(笑)。
 栃尾
栃尾なんかホント、バッサバッサ切っていく感じですよね、「そんなの意味がない」みたいな。
 武田
武田うん、で、その講演を文字起こししたのが、ご著書になっているので、面白いんですよね。
 栃尾
栃尾そっか、そっか。
 武田
武田読みやすいし。
 栃尾
栃尾忌憚なく言ってるっていうか。
 武田
武田そう、面白い、面白い。
 栃尾
栃尾私もね、Youtube観たことあります。
 武田
武田あぁ、Youtubeやっておられますね。
 栃尾
栃尾ご本人じゃなくて、誰かが収録したような。
 武田
武田協会があるんですよ。
 栃尾
栃尾あ、そっか、そっか。
 武田
武田テーラワーダ協会があって、協会の皆さんが長老の講演を出しておられる感じです。
 栃尾
栃尾はい、はい。すごい日本語流暢で。
 武田
武田そう、そう。
 栃尾
栃尾ドライな感じで、バッサバッサ切っている(笑)。
 武田
武田ドライな、バサバサ(笑)。
 栃尾
栃尾そうですね。なんか仏教の世界って、まあ、いわゆる「悟る」ってあるじゃないですか?
 武田
武田うん、うん。
 栃尾
栃尾あれって、スマナサーラ長老は悟ってると思いますか?
 武田
武田なるほどね、これね、ここに色んな考え方があって。
 栃尾
栃尾はい。
 武田
武田仏教を始めたのが2,500年前のインドのお釈迦様っていう人がいらっしゃって。
 栃尾
栃尾はい。
 武田
武田お釈迦様が悟りを啓いたんですよね。
 栃尾
栃尾うん、うん。
 武田
武田で、お釈迦様が悟ったのを「我々も、お釈迦様の教えに従ったら悟れるだろう」ということで、皆修行を始めたわけですよ。
 栃尾
栃尾うん。
 武田
武田で、それで色んな修行があって。で、テーラワーダとかですね、長老がやってるもの、仏教とかっていうのは悟りのためのプロセスがすごく綿密に作られてる、プログラムが。
 栃尾
栃尾はい。
 武田
武田で、それをやればやるほど悟りに近づくっていう考え方があって。で、一方で、日本仏教っていうのは、「そうは言っても悟れないよね」っていうところから実は始まってて。
 栃尾
栃尾そうなんだ。はい、面白い。
 武田
武田そうなんですよ。だから、いくら頑張ってやっても、「いや、煩悩ってあるじゃん」とか、「いくらそんなに鍛えたとしても,悲しい気持ちとか、腹が立つ気持ちって湧いてくるから、いや完璧な人間にはなれないよね」って。じゃあ、そんな人間がどうやって仏教していくのかっていうので発展して行ったのが、中国から日本にかけて来た大乗仏教っていうものの流れなんです。
 栃尾
栃尾ふーん。
 武田
武田ちょっと考え方が違うんですよね。
 栃尾
栃尾へぇ。じゃあ、武田さんのスタンスとしては、「いや、悟れやしないよ」っていう感じ?(笑)
 武田
武田(笑)僕はね。
 栃尾
栃尾いや、いや、人間は。
 武田
武田悟りの議論って、これ結構大事なのが、「人が悟れてるかどうかの判定」ってあんまりすると議論がおかしくなっちゃうんですよ、実は。
 栃尾
栃尾そうなんですね。
 武田
武田「あの人は悟れてるよね」とか、「悟れてないよね」とかって外から言うのって、やっぱりその人の心ってわからないのに決めつけちゃうじゃないですか。
 栃尾
栃尾はい。
 武田
武田そうじゃなくて、あくまでやっぱりこれって自分に向けた言葉にしなきゃいけなくって。
 栃尾
栃尾ふーん。
 武田
武田自分は悟れてるのか。
 栃尾
栃尾うん。
 武田
武田もっと言うと自分は悟りに近づくような生き方が出来てるかどうか。
 栃尾
栃尾うん。
 武田
武田っていうのを問い直すのは、あくまで自分に向けていかないと、「あの人が」とか、「この人が」とか言ってると、ちょっと話が変な方向に行っちゃうんですよね。
 栃尾
栃尾ふーん。じゃあ、あくまで自分が、でも、まあ、「悟った」という風に完了するというよりは、「悟りに向かってる」という風に。
 武田
武田そう、そう。あ、でね、そうなんですよ。で、悟りっていうと、いきなりモノの見え方が変わって、世界が変わったみたいな。
 栃尾
栃尾神になるみたいなね(笑)。
 武田
武田そう、そう。イメージあると思うんですけど。
 栃尾
栃尾はい。
 武田
武田でも、実はね、もともとは「目覚める」みたいな意味だったんですよ。
 栃尾
栃尾うん、うん。
 武田
武田寝てた人が目が覚めるみたいな。
 栃尾
栃尾そういう字書きますもんね、覚めるっていう(覚り)。
 武田
武田そう、そう。目覚めるみたいな感じなので、なんか寝てたり、ぼんやりしてたら外の世界よく見えないけど、よりクリアに見えるみたいな感じなので。
 栃尾
栃尾はい。
 武田
武田悟ったような心の状態に近づけることはもちろんできるし、悟れるような心の鍛え方っていうのはやっぱりできるわけで。
 栃尾
栃尾はい。
 武田
武田じゃあ、それが皆が自分ができてるかどうかっていうのは判定できるはずなんですよね。
 栃尾
栃尾うん。
 武田
武田心がしっかりコントロールできていて、掴めてるときっていうのは、やっぱり目覚めてるときですけど、怒ってるときとか、イライラしてるときって全然冷静に見えないですよね、色んなことが。
 栃尾
栃尾うん、うん。
 武田
武田ああいうときっていうのは、やっぱり悟りとは遠い自分にあるっていう感じになるんですね。
 栃尾
栃尾うん、うん。
 武田
武田状態像っていうね。
 栃尾
栃尾なるほど、人によっても、近いときもあるし、遠いときもあるって考え方ですか?
 武田
武田の方が、人間の実態には近いかなと僕は思います。で、これもね、色んな理論が実はあって。
 栃尾
栃尾へぇ。
 武田
武田そういう考え方。日本はどっちかっていうとそっちですよね。
 栃尾
栃尾はい、はい。波があるみたいな。
 武田
武田うん。
 栃尾
栃尾へぇ。いや、なんか本当に自分が怒っちゃったときとか、イライラしちゃったときとか、「未熟だなぁ」みたいな。別にまあ普段悟りを目指しているわけじゃないですけど、「なるべくこうそういうことに惑わされない自分になりたい」みたいに思うわけなんですよ、私なんかは。
 武田
武田うん、うん。
 栃尾
栃尾だから、「すごい未熟だな」って思うけど、「まあ、そういうときもあるよね」って感じですか?
 武田
武田そうなんですよね、その「未熟だな」とか落ち込むときとかっていうのがあるじゃないですか。
 栃尾
栃尾はい。
 武田
武田それをなんか「いや、まあ、こんなときもあるさ」とかって言って頑張れるときって、まあ、でも、言うても元気なときじゃないですか?
 栃尾
栃尾うん。
 武田
武田元気なときはできるんですよ。まあ、元気なときはそれでもいいし。
 栃尾
栃尾はい。
 武田
武田でも、一方でそれができないようなどん底にいる状態っていうのが、人生の中でやっぱりいくつかあって。
 栃尾
栃尾うん。
 武田
武田圧倒的に傷つけられたときとか。あとは、自分の病気とか、大事な人が亡くなったとか、自分の死とか。で、そういうものが目の前に来たときには「いや、まあ、いっか」とかって言えないじゃないですか?
 栃尾
栃尾なるほど、はい。
 武田
武田そういうときに悟りのクリアな気持ちでいられるっていうのは、まあ、理想的なんですけど、それって人間ってやっぱりちょっと難しいわけで。
 栃尾
栃尾はい。
 武田
武田そういうときに、まあ、浄土真宗でいうと、あのぉ、阿弥陀如来、「南無阿弥陀仏」の阿弥陀如来なんですけど。
 栃尾
栃尾はい。
 武田
武田阿弥陀如来っていうのは、そういうのが出来ようが出来まいが、無条件に支えてくれる存在があるんだっていうことを言うわけですよ。
 栃尾
栃尾ふーん。
 武田
武田そうなると、なんか自分で「まあ、いっか」って言えようが言えまいが、大丈夫な世界があるっていうのをひたすら言い続けるのが仏教で、で、これって自分で思えないじゃないですか?
 栃尾
栃尾はい。
 武田
武田「自分で大丈夫」って思えないから、それを周りから価値観として、「こういう世界があるんだよ」っていうのを、提示し続けるのがお坊さんの役割かなっていう感じですね。
 栃尾
栃尾ふーん。
 武田
武田ややこしい話ですね(笑)。
 栃尾
栃尾(笑)自分で思えないけど、そういう風に周りから言ってもらうことで、少しずつ回復していくみたいな感じですか?
 武田
武田うーん、なんかね、回復できても、できなくてもいいんです、実は。
 栃尾
栃尾なるほど、はい。
 武田
武田例えば、今、僕も椅子に座ってるんですけど。
 栃尾
栃尾はい。
 武田
武田この椅子って、なかったらここに居れないじゃないですか? で、椅子がここにあるためには、床が必要なんですよね。
 栃尾
栃尾はい。
 武田
武田で、床がここにばっちり立ってるためには、この地面がしっかりしてなくちゃいけなくって。で、こういう自分が今ここにいる、存在できてるっていうことの時点で、すでに実は、色んなものの力によって支えられて、ようやくここに安定して座ってるっていうことがあって。で、この目に見えないし、普段は考えもしないような力っていうものが、周りにいっぱいあって支えてくれている。で、「これを仏と呼ぼう」っていうのが、仏教の基本なんですよね。
 栃尾
栃尾ほぉ。
 武田
武田で、「その目に見えない支えてくれている力に気付いていきましょう」というのが、仏教的な生き方っていうことですね。
 栃尾
栃尾へぇ。
 武田
武田だから、その中で自分が善い行いができようが、できまいが、実はあんまり変わらない。椅子は椅子。椅子は変わらない。椅子の上で、腹を立ててようが、じっと座っていようが椅子は変わらない。
 栃尾
栃尾うん。
 武田
武田だけど、「仏様、悟りに近づきたいんだったら、怒りはなるべく抑えよう」っていう話なんですね。
 栃尾
栃尾うん、うん。
 武田
武田ややこしいですね(笑)。
 栃尾
栃尾へぇ。「それに、支えてくれるものに感謝しよう」っていう話でもないわけですね?
 武田
武田感謝はもちろんしようっていう話ではあるんですけど、感謝ができる人はそりゃもちろんした方がいいんですよ。ただ、感謝をしたから救われるとかじゃなくて、この救われているこの世界の構造っていうのはもう「在りき」なんですよね。
 栃尾
栃尾もう救われていると。
 武田
武田そう、そう。「あなたがどんな人間であっても、大丈夫っていうことになってる」と。
 栃尾
栃尾うん、うん。
 武田
武田で、「それに気付けたら感謝をしてくださいね」っていう感じですよね。
 栃尾
栃尾ふーん、その……。
 武田
武田ややこしい論理なんですよ(笑)。
 栃尾
栃尾はい、はい、普段こうすべきとか、こうした方がいいみたいな固定観念を崩してくれるような感じがしますよね。
 武田
武田そう、そう。そうなんですよ。だから、例えば、最近で僕も必要だなと思うのが、いわゆる自己啓発みたいな情報とか、世の中で成功するためのノウハウみたいなものが、まあ、いっぱいあるじゃないですか?
 栃尾
栃尾はい。
 武田
武田そういうのってやっぱりすごく大事で、そこで学んでやっていくっていうのは必要なんですけど、その価値観だけになっていると、そこで上手くいかなかったときに「俺は負け組だ」ってなっちゃうんですよね。
 栃尾
栃尾うん。
 武田
武田「もうダメだ、立ち直れない」ってなるんですけど。
 栃尾
栃尾はい。
 武田
武田「いや、そうじゃない」と。その道っていうのは、本当に人生の中の小さいところで、試しに色々やってるだけで、上手く行こうが行くまいが、仏目線で見ると全部すごく小さいことなんですよね。
 栃尾
栃尾うん。
 武田
武田人間のやってる行いなんていうものは、成功しようが、失敗しようが大したことではないっていうような、すごい大きな視点でモノを観る、人生を眺めることができるっていう価値観を自分の心の中の一歩に、一個持っておけば、目の前でやってることっていうのが、傷つけられても、上手くいかなくても大したことじゃないって思える自分になるので、仏教の柱っていうのを持っているとブレにくい自分っていうのが作れるなっていう風に思ってますね。
 栃尾
栃尾なるほどね、逆にその、これは極端なことかもしれませんけど、そっちに振れ過ぎちゃって日常がどうでもよくなっちゃうみたいなことはないんですか?
 武田
武田あります、ありますよ。
 栃尾
栃尾(笑)ありますか?
 武田
武田そりゃぁ、いっぱいある、いっぱいある(笑)。で、そういう人がやっぱり格好いいお坊さんになってますよね、そういう人って。
 栃尾
栃尾えー、「頑張らなくてもいいじゃん」みたいな。
 武田
武田「もう、なんもいい」と(笑)。
 栃尾
栃尾うん、うん。
 武田
武田それで「山奥で儂は静かに暮らす」みたいな格好いいお坊さんって、世の中いっぱいいますからね、ホント。
 栃尾
栃尾へぇ。
 武田
武田結構私も尊敬する人やっぱりいっぱいいますけど。
 栃尾
栃尾はい。
 武田
武田「本当、この人お坊さんらしいな」と思って、「素敵だな」と思う人やっぱりいて。
 栃尾
栃尾ふーん。
 武田
武田で、まあ、そういうスタイルもあるし、まあ、僕なんかは、一方で「誰に何を言われても怖くねぇから、どんどんYoutubeでもなんでもやったろうかい」みたいな感じの(笑)。
 栃尾
栃尾うん、うん。
 武田
武田ちょっと別スタイルで行ってるんですけど。
 栃尾
栃尾うん、うん。
 武田
武田それもなんかあれですよ、最初、「叩かれるからどうの」とか、「アンチがどうの」とか皆言うんですけど、「いや、そんなの大した話じゃない」と。
 栃尾
栃尾確かにね。
 武田
武田「届けるのがお坊さんの役割です」「Youtubeをやろうじゃないか」ということで、やってる感じですよね(笑)。
 栃尾
栃尾うん、うん。その仏の視点から見れば大したことじゃない、と。
 武田
武田そう、そう、はい。
 栃尾
栃尾ずっとそこに居続けることはできないから、日々、やっぱり細かいことで一喜一憂したりするんだけど。
 武田
武田あぁ、そうですね。
 栃尾
栃尾ときどき、やっぱりそこに戻るみたいな感じですかね? 感覚的には。
 武田
武田そうですね。我々なんかはやっぱり朝晩お参りしたりとか、日中でもお参りして手を合わせる機会がいっぱいあるんですけど、手を合わせて「南無阿弥陀仏」と合掌するのが、そのリセットするときなんですよね。
 栃尾
栃尾ふーん。
 武田
武田「手を合わせて念仏したら、その声の仏様になって自分のところに来てくれる」っていう言い方をするんですけど。
 栃尾
栃尾うん、うん。
 武田
武田そのときに、「いや、あなたちょっと落ち着きなさい」って言ってるかもしれないし、「いやいや、そんな細かいことでクヨクヨせずに突き進め」って言ってくださってるかもしれないし、そういう考え方を仏視点から切り替えるみたいなスイッチっていうのは、すごく役に立つと思う。で、これを1日の中に何回か持つことができたら、かなり心にゆとりをもって、色んなことに取り組めるでしょうね。
 栃尾
栃尾なるほど、自分の心の中に何か気付かせるスイッチみたいなことなんですね。
 武田
武田うん、うん、そう、そう。
 栃尾
栃尾あぁ、そうなんだ。最後にもう一つあれなんですけど、何のために悟るんですかね? 悟りたいって思うんですか?
 武田
武田これは、もうね、明らかにですね、自分が幸せになるためって感じで。
 栃尾
栃尾そっか、苦しみ……。
 武田
武田で、自分が苦しみから解決して豊かに生きるためにやっぱり悟りたいという感じですね。
 栃尾
栃尾うん、うん。なんか苦しみがある人生の方が美しいみたいなことはどう思いますか?
 武田
武田(笑)苦しみはあるんですよ。一切皆苦なんですよ、ベースは。
 栃尾
栃尾そっか、そっか。
 武田
武田苦しみしかないんですよ、もう人生っていうのは。もう苦しみしかないんだけど、その苦しみをどう乗り越えるかっていうところを目指していくので、もう永遠の問いですよね、悟りって。
 栃尾
栃尾ふーん。
 武田
武田もう問い続けていくんですよ、人生をかけて。
 栃尾
栃尾うん、うん。
 武田
武田だから、ここで終わりとかっていうんじゃなくて。
 栃尾
栃尾はい。
 武田
武田で、よく言いますけど、剣道とか柔道って「道」がついてるんですよね、仏道もそうですけど。
 栃尾
栃尾うん。
 武田
武田剣道も、柔道もそうですけど、八段まで行ったら終わりじゃないじゃないですか?
 栃尾
栃尾あぁ。
 武田
武田達人の人も結局ずっと練習するじゃないですか? 剣を振り続けるわけです。だから、仏道も一緒で、悟りっていうのはここまできたら終わりじゃなくて、そこから先も修行はするし、お経は読むしっていうのをやる。だから、まあ、長老もそうですよね、スマナサーラ長老もいまだに瞑想はするし、皆とこうやって話をしながらたぶん自分を深めておられるんだろうなっていう意味では。
 栃尾
栃尾そっか。
 武田
武田人生をかけてずっと問い続ける。悟りとはっていう。
 栃尾
栃尾なるほどねぇ。この短い時間じゃあ、なんか分かりようがないですけれども。
 武田
武田(笑)。
 栃尾
栃尾なんとなくその取っ掛かりはね。
 武田
武田そうですね。
 栃尾
栃尾「こういうのを書いてある本をちょっと読みたいな」みたいな気持ちになったりしますね。
 武田
武田あと、Youtubeをご覧くださいませ。
 栃尾
栃尾そうですね、『仏心チャンネル』を。
 武田
武田『仏心チャンネル』を皆さん観てください。
 栃尾
栃尾観させていただきます。
 武田
武田仏教、色んなね。
 栃尾
栃尾そっか、そっか、面白い。
 武田
武田Youtubeラクですよ、本より(笑)。
 栃尾
栃尾確かに(笑)。
 武田
武田観てればいいから。本はやっぱり読むの大変ですからね。
 栃尾
栃尾そうですね、ありがとうございます。じゃあ、えっと、今回最後になりますけど、今まで5回ね、ありがとうざいました。
 武田
武田はい、ありがとうございました。
 栃尾
栃尾では、以上、栃尾江美と。
 武田
武田武田正文でした。
<書き起こし、編集:折田大器>
↑音声で聞きたい方はこちら
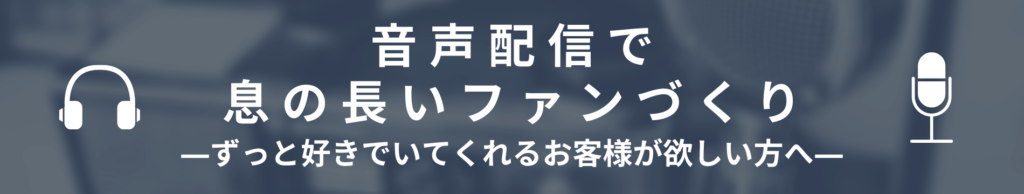
ストーリーエディター栃尾江美と音声配信を始めたい! という方はこちらへ