
ものづくりをする人なら「完璧を作ろうとしてしまう問題」に付きまとわれるものではないでしょうか? スーパーの売り場も似た問題がある層です。個人のブログですらありますよね。その話からスタートし、自由に会話してみました!
 栃尾
栃尾クリエイティブの。
 宮田
宮田反対語。
 栃尾
栃尾こんにちは、ストーリーエディターの栃尾江美です。
 宮田
宮田こんにちは、宮田匠です。
 栃尾
栃尾このポッドキャストは私、栃尾江美が好きな人やお話したい人をお呼びして、クリエイティブに関することや哲学的なことを好き勝手に話す番組です。えーでは、いつも話がね、いろいろと盛り上がってしまいますが、今回も宮田さんよろしくお願いします。
 宮田
宮田(笑)よろしくお願いします。
 栃尾
栃尾(笑)はい、えーと、まあ、ずーっとねスーパーとメディアとか、アウトプットみたいなことで話してるんですけども、完璧を作ろうとしてしまう問題があるということなんですよね。
 宮田
宮田はい、なんかそのあたりはイケそうじゃないかなと思って。
 栃尾
栃尾(笑)。
 宮田
宮田(笑)。
 栃尾
栃尾文章はね、めっちゃありますよね。売り場もあるんですか? でも?
 宮田
宮田はい、売り場も……、これね、ちょっと、まず僕の現段階というか、僕ホント、ペーペーなんで。
 栃尾
栃尾はい。
 宮田
宮田この分野に関しては、いったら何て言うんですかね、文章で言うと、文章書き始めましたみたいなぐらいのところにいるんで。
 栃尾
栃尾はい。
 宮田
宮田それでいくと、何もわからないわけじゃないですか(笑)。
 栃尾
栃尾はい。
 宮田
宮田例えば、ピーマンってどれぐらいの時期が売れ始めるのかとかも全然わからないので。
 栃尾
栃尾あぁ。
 宮田
宮田完璧を作ろうとするのはやっぱり無理なんですけど、でも、やっぱり完璧を作ろうとしちゃうんで、いかにその何て言うんですかね、段階的にというか、バッファーというか、を作って進めていくかみたいなのをすごい考えます、最近。
 栃尾
栃尾完璧ってどういうことなんですか? どうなったら完璧なんですか? 完売したら?
 宮田
宮田完売、ぴったり売れるとかもそうだし、あとは、何て言うんですかね、どこに何を並べるかで言うと、よく売れる並びって言うんですかね、にできるかとかかなぁ。
 栃尾
栃尾うん、うん、よく売れる、はい。なんか文章に関しては、私自身は、もはやそんなにないです。
 宮田
宮田あぁ、とっちーさん自身は。
 栃尾
栃尾はい、完璧を目指すっていうことが。
 宮田
宮田はい。
 栃尾
栃尾でも、私、アウトプット相談って私、個人的にやってて。
 宮田
宮田はい。
 栃尾
栃尾それで来てくださる方は、すごくやっぱり完璧を求める。まあ、完璧ってご本人が言うわけではないですけど、すごく「ちゃんとしたものじゃないと出したくない」みたいな方は多いですね。
 宮田
宮田うん、うん。
 栃尾
栃尾で、たぶん売り場と違うのは、売り場っていうのは結局、毎日どうにかしても、どうであっても並べなくてはいけないじゃないですか?
 宮田
宮田あぁ、そうですね、確かに、はい。
 栃尾
栃尾そう。だから完璧を求めようとしてもやっぱり時間が許さないからできないみたいなのがあると思うんですけど。
 宮田
宮田うん、うん。
 栃尾
栃尾文章って完璧なものができてから出そうっていう風に判断できちゃうから、いつまでも出さないってことがあり得るんですよね。
 宮田
宮田そうですよね、温め続けるみたいな(笑)。
 栃尾
栃尾そう、そう、そう(笑)。
 宮田
宮田(笑)。
 栃尾
栃尾それが多分違って、よくないんだと思いますね。
 宮田
宮田うん、うん。
 栃尾
栃尾だから売り場みたいに、毎日、なんか否が応にも出さざるを得ないみたいな状況の方が私はずっといいと思ってますね。
 宮田
宮田(笑)そうですよね。で、売り場とかも多分、決まり切っている部分もあれば、新しくやってみようみたいな部分もあって。
 栃尾
栃尾うん。
 宮田
宮田その新しくやってみようみたいな部分は、もうさっき今言われたことと全く同じで。
 栃尾
栃尾はい。
 宮田
宮田例えば、なんか新しく玉ねぎの箱売りを展開してみようっていうアイデアがあって。
 栃尾
栃尾うん。
 宮田
宮田でも、出してみないと売れるかわからないし、発注してみないと、モノが届かないとその陳列の方法って考えられない部分とかもあると思うんですけど。
 栃尾
栃尾あぁ。
 宮田
宮田それってやってみないとわからないんで、やらないっていう結論に至る部分もあるじゃないですか。
 栃尾
栃尾なるほど、確かに。
 宮田
宮田はい、だからその辺もどれぐらいまで失敗を許容できるかもあるんですけど、まず、とりあえず、なんか発注して出してみるみたいなのは、とりあえず大事なのかなっていうのはありますね、やっぱ。
 栃尾
栃尾そうですね、あと違いは、個人のアウトプットなんて、別にそんな、成功も失敗もそんなにないんですけど。
 宮田
宮田はい、はい。
 栃尾
栃尾売り場の場合は、もう明確に結果が見えちゃうっていうところが違いでしょうね、シビアな(笑)。
 宮田
宮田あぁ、あ、そういう視点で言ったらそうですよね、組織でやってるから。
 栃尾
栃尾うん。
 宮田
宮田売り上げの責任はあるし。
 栃尾
栃尾はい。
 宮田
宮田でも、確かに個人で例えばその辺の朝市のところに持っていくんであれば自由ですもんね。
 栃尾
栃尾うん、そうですよね。で、個人のブログも書いたからってそんなになんか、すごくいいことがあるわけでも、すごく悪いことがあるわけでもないから、ちょっとそのわからない恐怖心みたいなことがやめてしまうみたいなことはあると思うんですけども。
 宮田
宮田ふん、ふん、ふん。
 栃尾
栃尾そんな感じですね。
 宮田
宮田はい。
 栃尾
栃尾私がその完璧を作ろうとしてしまう問題、私自身にはないっていうのは、もうちょっと話してもいいですか?(笑)
 宮田
宮田あ、はい、もちろん、はい(笑)。
 栃尾
栃尾それは、自分の中でクオリティの基準が出来てるからですね、たぶん。
 宮田
宮田それはどういうことですか?
 栃尾
栃尾あの、文章をこれぐらい書けたらもうOKっていう、今までの経験上ですね。
 宮田
宮田あぁ、そういうことか、はい。
 栃尾
栃尾はい。「これはまだもうちょっと推敲しないとヤバいだろう」っていうのとか。
 宮田
宮田はい。
 栃尾
栃尾まあ、大体読み直してわかるんですけどね。
 宮田
宮田はい。
 栃尾
栃尾読み直してみて、「これぐらいスムーズに読めていれば大丈夫だな」みたいな、そういうクオリティ……、80点、これなら80点ぐらいかなっていう基準があって。
 宮田
宮田はい。
 栃尾
栃尾それを越えたら、もうエイヤで出しちゃうっていう。
 宮田
宮田はい、はい、はい。
 栃尾
栃尾自分の基準があるからだと思います。
 宮田
宮田それ大事ですよね。なんか最初にやり始めたときって、0か100かみたいな感じだと思うんですけど。
 栃尾
栃尾(笑)はい。
 宮田
宮田その60点以上とか、何て言うんですかね、その間の部分、「ここからここくらいまでに入ればいいだろう」みたいなのができ始めると。
 栃尾
栃尾うん。
 宮田
宮田そうやって出しやすくもなるし。
 栃尾
栃尾はい。
 宮田
宮田一旦、60で出して、80、100に上げていこうとかもできますよね。
 栃尾
栃尾そうですよね。そう、そう。ちょっとだから、もうこういう、例えば、インタビュー……、ここのメディアのインタビュー記事はこれぐらいだよねってある程度わかってるやつは、最初からちょっと高得点狙えると思うんですけど。
 宮田
宮田はい。
 栃尾
栃尾全然わかんないやつは、その60点ぐらいで一旦出すみたいな。
 宮田
宮田(笑)。
 栃尾
栃尾ところはありますよね。初めてやるジャンルとか。
 宮田
宮田そうですよね。最初の段階はやっぱり大事ですよね。で、Aのジャンルで、そういう一旦、その、ちょっとずつ高めていくっていう習慣が付けば。
 栃尾
栃尾はい。
 宮田
宮田次、どこか別のところで新しいことをやるときにも、一旦、最初に出すのは絶対100とか80ではなくて、30、40しかないんだっていうマインドっていうんですかね(笑)。
 栃尾
栃尾そうですね、なるほど。
 宮田
宮田はい、それが大事だなって、僕も転職してみて、転職っていうか、新しい分野に来てみてすごい思います。
 栃尾
栃尾なるほどぉ。今って、どうしてるんですか? その、売り場を作ってみてから、一旦、上の人に見てもらうみたいな。初めての場所だと。
 宮田
宮田はい、見てもらうのと、なんか出してみたやつ、結局売れるか、売れないかが返ってくるんで。
 栃尾
栃尾はい。
 宮田
宮田「あ、ダメだったな」とか。
 栃尾
栃尾うん、うん。
 宮田
宮田「これでやるんだったら、この商品の横に置いたのがダメだったのかな」とか。
 栃尾
栃尾うん、うん。
 宮田
宮田そういうのはすごく、一旦、出してみてから調整していく感じですかね。で、あとは、ちょっと話が逸れるかもしれないんですけど。
 栃尾
栃尾はい。
 宮田
宮田「これぐらいまでなら試しても大丈夫」みたいなのを最初にちゃんと考えておいて。
 栃尾
栃尾あぁ、はい、はい。
 宮田
宮田ちょっとさすがに、例えば、やってみたいからといって、意味わからない商品をいきなり1,000個とか発注したら、傷んじゃうけど。
 栃尾
栃尾うん、うん。
 宮田
宮田100個ぐらいまでなら、ちょっと適当に出してみて、売れなくても、まあ、なんとか後でやりくりできるだろうみたいなのを一旦、相談しておいてからやります、今は(笑)。
 栃尾
栃尾あぁ、それは確かにありますねぇ。なんか私はお笑い……、お笑いっていうか笑える記事ってほとんど書かないんですけど。
 宮田
宮田はい。
 栃尾
栃尾一回インタビューした人がすごい面白い方だったことがあって。
 宮田
宮田(笑)はい。
 栃尾
栃尾で、それを原稿にも結構出してみたことがあるんですよね。
 宮田
宮田あぁ、はい、はい。
 栃尾
栃尾うん、で、すごい私的にはチャレンジだったんですけど。
 宮田
宮田はい。
 栃尾
栃尾「こんな感じで出すのどうでしょうね」みたいな、ちょっと「没ったら没ったでいいや」みたいなぐらいの感じでちょっとチャレンジして出したことがあって。
 宮田
宮田はい。
 栃尾
栃尾全部の、文章全部を面白くするんじゃないけど、ちょっとこう面白いポイントをちょこちょこ入れるみたいなことはやったことがありますね。
 宮田
宮田うん、うん。
 栃尾
栃尾そういう風に、ちょっと枠を外れるみたいなのって。
 宮田
宮田はい、そう、まさに、はい。
 栃尾
栃尾そう、そう、確かに、ちょっとずつやれると楽しいですよね。
 宮田
宮田はい、そうなんですか(笑)。
 栃尾
栃尾そう思う。
 宮田
宮田外れ過ぎたら完全に別物になっちゃったりとかして。
 栃尾
栃尾はい、はい。
 宮田
宮田ヤバいんだけど。
 栃尾
栃尾うん、うん。
 宮田
宮田でも、やっぱり外れてみたいし(笑)みたいな。どれぐらいまで外れてもいいのかみたいな、その、最初わかんないじゃないですか?
 栃尾
栃尾はい。
 宮田
宮田そこら辺をちょっと把握するのって大事なのかもなとか思いますね。
 栃尾
栃尾そうですね、それ、なんかまた前回と同じように、ミュージシャンの話になるんですけど(笑)。
 宮田
宮田(笑)はい。
 栃尾
栃尾ミュージシャンってこういう曲調で、こういうファンが付いているってもう決まってるじゃないですか?
 宮田
宮田そうですよね、人気になってきたら。
 栃尾
栃尾基本的にはね。
 宮田
宮田はい。
 栃尾
栃尾だけど、本人もやっぱりちょっと外れたいわけですよね。
 宮田
宮田はい。
 栃尾
栃尾それをどこまで外すか。まあ、外れ過ぎたら新しいユニットを組まなきゃいけないのかみたいな(笑)。
 宮田
宮田あぁ、いや、ホントそうですよね。
 栃尾
栃尾そう、そう、そう。
 宮田
宮田お店のコンセプト変えないといけなくなっちゃうとかありますもんね。
 栃尾
栃尾そう、そう、そうです、そうです。だから、その今のグループ内でどこまで外すのかみたいなのって、言語化しないにしても、すごいやっぱり考えてると思いますね。
 宮田
宮田うん、うん、うん。
 栃尾
栃尾だからメディアもそうですけど、このメディアでどこまでちょっと外していくのか、広げていくのかみたいなこともありますね。
 宮田
宮田はい。
 栃尾
栃尾で、「そこまでやるのは、うちのメディアの役割じゃないよね」みたいなことも全然ありますし、で、ちょっとチャレンジしてみてっていう。でも、基本的には、そのメディアの王道みたいな読者が付くわけじゃないですか?
 宮田
宮田はい。
 栃尾
栃尾でも、外す場合って、王道の人が興味あることとちょっと外れてるはずだから、最初ってそんなにビューもいかないはずなんですよね。
 宮田
宮田そうですよね。
 栃尾
栃尾そうですよね。で、それをメディアの幅を広げるために、ちょっと外れたところを頑張って、どうやって読者を増やしていくかってやるのか。
 宮田
宮田はい。
 栃尾
栃尾それとも一回やって、ビューが行かなかったから、「あぁ、ダメだね」って思うのかっていうところも違うと思いますね。
 宮田
宮田確かに。どれぐらいの期間やらないと検証が終わらないのかみたいな感じですかね。
 栃尾
栃尾そうです、そうです。例えば、スーパーだったら、「いや、もうちょっと小洒落た層もお客さんとしてほしいんだよね」みたいなことを言ってて。
 宮田
宮田はい。
 栃尾
栃尾で、ちょっと小洒落たコーナーを置いたら売れなかったからもうやめちゃうのか。
 宮田
宮田はい。
 栃尾
栃尾それともその小洒落たコーナーをずーっとやってて、やっぱりお客さんが増えるのを頑張るのかみたいな。
 宮田
宮田はい。
 栃尾
栃尾その粘り強さみたいなところも(笑)。
 宮田
宮田(笑)。
 栃尾
栃尾ありそうだなって思いました。
 宮田
宮田あ、確かにありそう。
 栃尾
栃尾ね。
 宮田
宮田絶対に長くやってみないとわかんないですもんね。その客層レベルで。
 栃尾
栃尾あ、そうです、そうです。それで客層が増えるかもしれないし、やっぱりダメかも……、最初はやっぱり新しいことをやると、そこまで人気が出ないというのが。
 宮田
宮田はい。
 栃尾
栃尾パターンとして多いんじゃないかなと思うので。
 宮田
宮田確かに。あと、それで言ったらいかに小さくテストしてみるかみたいなのもすごい大事な感じが。
 栃尾
栃尾うん、うん、うん。そうですね。結果が出やすいのは、きっと今のお客さんが潜在的に求めてたものみたいなことがわりとすぐ結果が出るんでしょうね。
 宮田
宮田ふん、ふん、ふん。そこが見つけられるか。
 栃尾
栃尾そうですよね。客層変えるまでいくとなかなか長期戦というか。
 宮田
宮田そうですよね、それになんか色々大きい問題になってきますもんね。
 栃尾
栃尾まあ、そうですよね、そのコンセプトみたいな問題になっちゃうから、そうだな。まあ、完璧を作ろうとするっていうところで、もう一回話を戻すと。なんかインタビューって。
 宮田
宮田はい。
 栃尾
栃尾わりと出たとこ勝負みたいなのがあるんですけど。なんかすごいインタビュー前に構成をガチガチに決めたい人っていうのも時にいるわけですね。
 宮田
宮田うん、うん、なるほど。
 栃尾
栃尾多分それは不安要素を減らしたいんだと思うんですけど。それはまあ予定調和なものはできるかもしれないけど、それで良い記事になることもあるんですけど。
 宮田
宮田ふん、ふん。
 栃尾
栃尾こうやっぱ、なんか、本当にその時だから出た面白いものみたいなのは求められないっていうか。
 宮田
宮田うん、うん。
 栃尾
栃尾そういうちょっとした完璧を求めるからこじんまりとしてしまうみたいなところはありますね。
 宮田
宮田あぁ、なるほど、いや、すごい、それ滅茶苦茶……、前の……、スーパー全然関係なくなっちゃうんですけど。
 栃尾
栃尾(笑)はい。
 宮田
宮田前の会社って、前の会社にいたときってよくワークショップしてたので。
 栃尾
栃尾あぁ。
 宮田
宮田僕結構、何だろう、事前に考えちゃってたので。
 栃尾
栃尾あぁ。
 宮田
宮田すごく、それずっと指摘されてたので、またなんか再び同じことを(笑)思い出したりも。
 栃尾
栃尾なるほど、そうなんですよね、でも、事前にあんまり決めないでおくと。
 宮田
宮田はい。
 栃尾
栃尾すごいつまんないになる会もあるっていうことですよね、たぶん。
 宮田
宮田(笑)そういうことですよね、はい。
 栃尾
栃尾そういうことですよね。でも、それも許容するかっていう。
 宮田
宮田そうなりますよね、幅がこう、最初に決めておけば幅が狭くなるんで。
 栃尾
栃尾そう、そう、そう。
 宮田
宮田はい。
 栃尾
栃尾でも、インタビューのよいところは。
 宮田
宮田はい。
 栃尾
栃尾記事にする時点でもう一回工夫できるので。
 宮田
宮田なるほど、そうですね、確かに。
 栃尾
栃尾はい、インタビュー自体そんなに盛り上がらなくても、「ここがいい言葉だったからここをちょっとフューチャーしようかな」って構成を変えられたりできるので。
 宮田
宮田うん、うん、うん。
 栃尾
栃尾結構つぶしが効くっていうのか、危険が少ないのかもしれないですね、ワークショップとか、ホントに現場のものと比べると。
 宮田
宮田インタビューってそうか、素材を集めてる段階ですもんね。
 栃尾
栃尾そうです、そうです。だから私は逆にやっぱりそこはちょっと曖昧なままチャレンジする方が楽しいのになって思ったりしますね、そう、そう。
 宮田
宮田それ、面白い。
 栃尾
栃尾ということで、そろそろまたお時間となりましたので(笑)。
 宮田
宮田(笑)。
 栃尾
栃尾終わりにしたいと思います。
 宮田
宮田はい。
 栃尾
栃尾以上、栃尾江美と。
 宮田
宮田宮田匠でした。
<書き起こし、編集:折田大器>
音声で聞きたい方はこちら
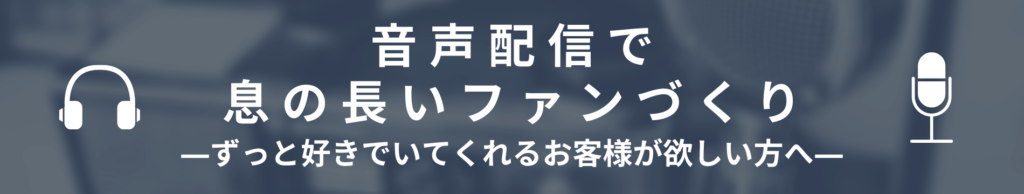
ストーリーエディター栃尾江美と音声配信を始めたい! という方はこちらへ